「見込み客」を集めるフロントエンド商品について
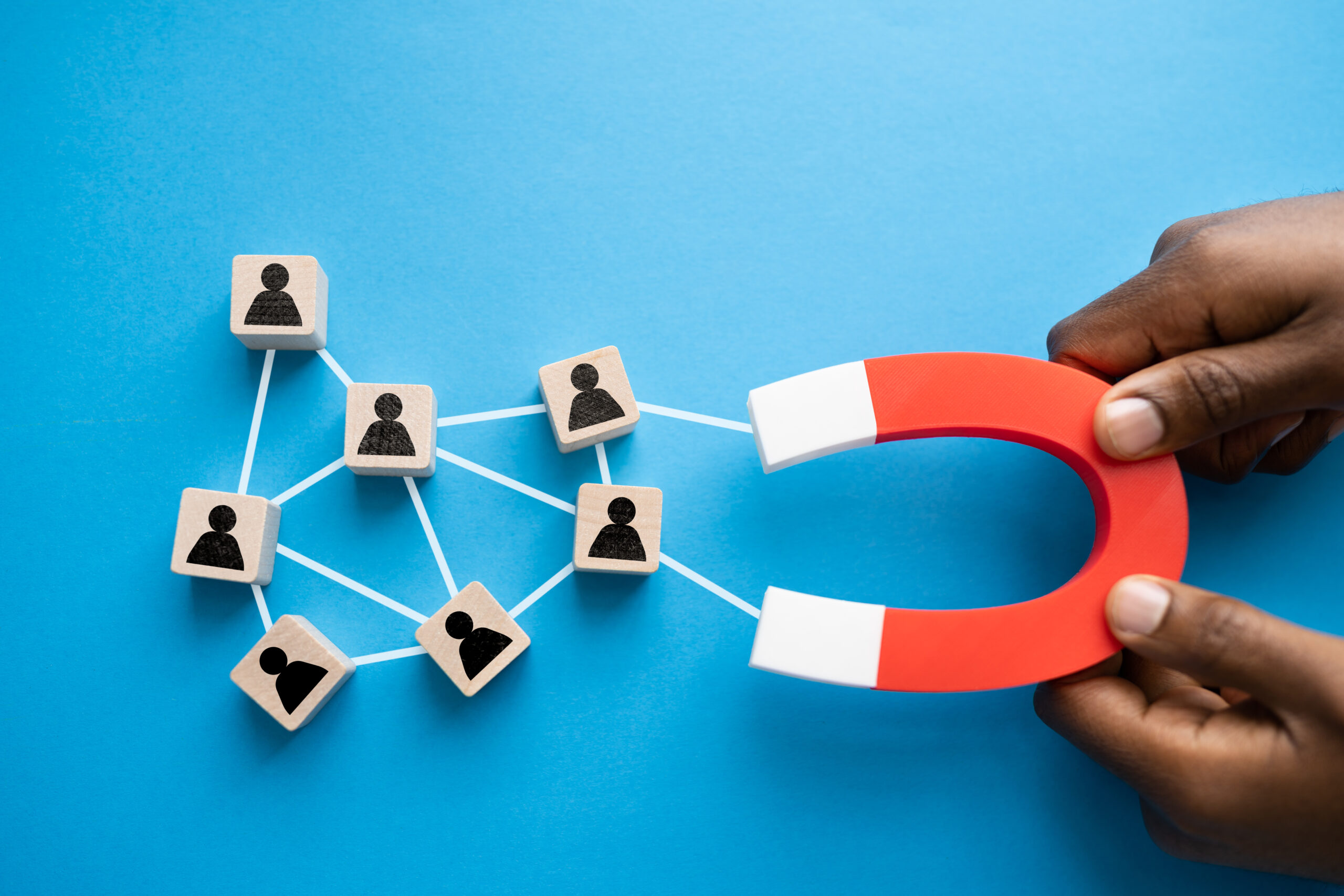
今日の解説はフロントエンド商品についてです。
フロントエンドという言葉、あまり聞き馴染みがない言葉かもしれませんが、例えば居酒屋のランチはフロントエンド商品です。
他にも、弁護士の無料相談や、住宅ホームの無料見学会もフロントエンド商品の1つです。実は、私たちの身の回りにはフロントエンド商品が溢れています。
そして、ダイレクト・レスポンス・マーケティングには、フロントエンドとバックエンドという考え方があるのですが、
・フロントエンドとは、そもそも何か?
・どんな商品やサービスならフロントエンドになるのか?
・フロントエンドの価格はいくらくらいが適切なのか?
・バックエンドの商品やサービスに繋がるフロントエンドは、どのように考えたらいいのか?
このようなことについて、解説していきます。
フロントエンド商品とは、そもそも何か?
まず、フロントエンド商品とは、そもそも何か?ということについて。フロントエンド商品とは集客商品。バックエンド商品とは、利益商品と呼ばれています。
フロントエンド商品(FE商品)=集客商品
バックエンド商品(BE商品)=利益商品
つまり、フロントエンド商品とは「採算度外視で、集客を目的として作られた商品」ということです。そして近年、このフロントエンド商品の重要性が益々高まっています。
なぜフロントエンド商品を作ることが重要なのか?
その理由は、顧客の商品やサービスに対しての不信感の増加です。
これはいわゆる情報商材の人には特に関係ある話なのですが、詐欺商品や詐欺のようなサービスが一昔前横行しました。例えば「1クリックするだけで1万円が手に入ります!」とか、「スマホを見ているだけで収入が手に入ります!」というような商品やサービスです。
顧客はそういった商品やサービスを購入すれば、本当に実現するんだと思って購入したのですが、結局は全て詐欺だったり、全くできないといったことが横行し、それがネット上に口コミとなり、益々情報商材が怪しいと思われ、顧客は滅多に商品やサービスを購入しなくなるという悪循環が起こったのです。
そしてこれは、情報商材に限った話ではありません。
例えば通販やネット上で販売している商品でも、同様のケースがありました。実際ある通販会社の商品について、扱っている会社の社長に「これ本当に効果あるんですか?」と尋ねたところ、「いや、ないんじゃない?」との回答が…。
つまり、このような詐欺まがいの商品やサービスが横行したため、滅多なことがない限り、顧客は商品やサービスを購入しなくなったというわけです。
そのため、利益が出るような高額商品やサービスを顧客が購入してくれなくなり、益々FE商品でお試しをしてからじゃないと購入しないという図式が成り立つようになりました。
そのため、フロントエンド商品を作らなければ、お客さんは、
・本当にここの会社大丈夫?
・本当にこの商品大丈夫?
と、疑うようになり、フロントエンドである程度の成果を出してもらわなければ、お客さんは商品・サービスを継続して購入してくれなくなっているということです。
そのため、フロントエンド商品で集客を行い、バックエンド商品で利益を上げるというのは、通販やインフォ系の商材だけでなく、ほぼあらゆる業種で必要になってきました。
ではフロントエンド商品を実際に作って運用している企業にはどのようなものがあるのか。フロントエンド商品を使って実際に集客を行っている企業の実例を少しご紹介します。
フロントエンド実例解説
1、通販企業
化粧品や食品の通販を行っている企業で、フロントエンド商品がない企業はほぼほぼ存在しません。なぜなら、通販事業では商品の違いが出しにくいため、まずはフロントエンド商品で顧客を集めて、リピートで稼ぐというビジネスモデルだからです。
例えば、やずや、ドモホルンリンクル、ドクターシーラボなどは全てフロントエンド商品を持っていますし、他の化粧品や食品を扱っている企業は、ほぼ全部の企業がフロントエンド商品を持っています。
2、弁護士・税理士
弁護士や税理士などもフロントエンド商品として、無料相談などを行っています。他にも昔税理士関連のクライアントさんがいらっしゃいましたが、そこで行っていたのが、「1円でも多く確保する相続」というような内容で、無料のPDFレポートを作成して集客したことがあります。
3、居酒屋・英会話教室
他にも居酒屋や英会話教室などのスクールでもフロントエンド商品でお客さんを集めています。居酒屋の場合だとランチ営業なんかはその典型例です。他にも、Line登録してくれたらビール1杯無料だったり、Line登録してくれたらケーキを1枚サービスするといったことをしているところもあります。
また、英会話教室などのスクールの場合は、初回無料レッスンだったり、体験会だったり、見学会を行っていますよね。それも購入のハードルを下げるフロントエンド商品の一つです。
4、インフォ系
オンラインコンテンツや、講座、セミナーを行っている会社も、フロントエンド商品で見込み客を集めています。
例えば、無料のPDFレポートだったり、無料のオンライン動画プログラムだったり、最近はチャレンジ企画というものもあります。
このように、様々な企業がフロントエンド商品を作り見込み客を集客し、近年、ほとんど全ての企業がフロントエンド商品を作り見込み客を集めています。
そしてほとんど全ての企業が、無料だったり、利益が出ないくらい安い価格設定を行っています。実はフロントエンド商品では、利益を出してはいけないと言われているのですが、その理由についてお伝えしましょう。
フロントエンドを無料(に近い金額)で行うべき理由
その理由は単純で、集客が年々難しくなっているからです。今から約20年前、まだガラケーが最盛期だった頃、1メールアドレスを集めるのに必要なコストは5銭から1円でした。それが今では、1メールアドレスあたり、1000円から3000円と、一体何倍になったんだ?というくらいコストが膨れ上がっています。
つまりそれだけ、集客が難しくなり、どんなビジネスでもお客さんを集めることが難しくなっているため、集客用の商品を「採算度外視で」用意しなければ、お客さんを集めることが、ほぼほぼ不可能になってきているということです。
では、フロントエンドにはどのような形態があるのでしょうか。
フロントエンドの形態について
大まかに分類分けすると、フロントエンドは、以下の9種類に分類できます。
1)無料提供やサンプル系
2)デジタルコンテンツ系
3)動画・音声系
4)コンサルティングや診断系
5)コミュニティ・イベント系
6)物理的な商品・サービス系
7)特典・割引・トライアル系
8)パーソナライズ・カスタマイズ系
9)楽しみやエンタメ系
厳密にいうと、それぞれ掛け合わせることもできるので、あくまで参考程度として考えてください。ではそれぞれのフロントエンドで、どのような形態・商品が考えられるか。解説していきます。
1)無料提供やサンプル系
まず紹介するのは、無料提供やサンプル系です。これは通販でもお馴染みですし、どんなビジネスを行っていても、大体活用できるフロントエンドなので、ここだけはしっかり見ておくのをオススメします。
・無料サンプル・有料サンプル(キット)
・無料トライアル・無料お試し
・無料試乗
・無料メンテナンス
・製品の試用版
・無料デモンストレーション
・無料の施設見学
・無料の製品レビュー集
・製品の無料貸し出し
・書籍の無料サンプル
・動画講座の無料サンプル
具体的にどんなフロントエンド商品が考えられるか。例えば、無料サンプルといえば、大体の化粧品通販が、無料サンプルや無料お試しを行っています。
他にも、製品の使用版はアプリやソフトを販売している場合。PlayStationでも、ゲームの無料体験を行っています。
あとは、書籍の無料サンプルといえば、Amazonがプレビューとして少し内容を見れるようになっています。(ちなみに書籍販売の際にプレビューが出来るようにすると、成約率が上がります。)
多くが無料提供となっていますが、実際はお試し版・試供品でも有料の場合があるので、それは自社のキャッシュフローとの兼ね合いで検討する必要があります。
2)デジタルコンテンツ系
次に紹介するのは、デジタルコンテンツ系です。デジタルコンテンツというと、インフォ系が思い浮かびますが、実業系でも使うことはできます。
実際過去、ある新聞の広告欄にQRコードを載せてPDFレポートをダウンロードしてもらうというのが出来るか確認したところ、「前例がないですが出来る」との回答をもらい実施したところ、、凄かったです。
・E-Book(電子書籍)
・ガイドブック
・ホワイトペーパー
・インフォグラフィック
・PDFコンテンツ
・動画講座トランスクリプト
・業界レポート
・チェックリスト
・フレームワーク
・テンプレート
・事例集
・スクリプト(台本)
・ツールキット
・エクセルシート
・クイズ、ジェネレータ(占い系)
・業界の現状、業界の予測
・ニュースレター
・DIYガイド
・課題解決ワークブック
・自己評価シート
・オーディオブック
・電子雑誌、マガログ
・無料オンラインゲーム
・ブログ、記事
具体的にどんなフロントエンド商品が考えられるか。例えば、BtoBの企業だと事例集や業界の先行予測なんかが考えられます。ちなみに、BtoBの業界レポートは、一つ99万円とかで売られてたりします(それだけ欲しいという欲求が高いということですね…)
他にもクイズ、ジェネレーターなんかは占いだとあるあるですし、チェックリストなんかもよくあります。(鬱病チェックリストなんかもそうですよね。)
他にも、『海外情報を元にしたうさぎの飼育ガイド』というガイドブックや、『MyAspを導入してメールマガジンを始める方法』というチュートリアル系や、『マーケティングメッセージを作るファーストステップ』というPDFレポートなんかも考えられます。
3)動画・音声系
そして次に、動画・音声系です。先ほどのものとあまり変わらないと思うかもしれませんが、動画・音声系で分けたのは、動画・音声系は、リアルタイム制・確実に最後まで見てもらえる可能性が高いものとなるため分けました。
・動画講座オーディオ
・教育用オーディオ
・ポッドキャストシリーズ
・教育用の動画
・動画講座
・ウェビナー
・動画講座DVD無料配送
・オーディオ講座CD無料配送
・ウェビナー録画とリプレイ
・オーディオブック
・無料インタビューシリーズ
・Vlog(ビデオブログ)
・ビデオレビュー集
・無料インタラクティブワークショップ
・ライブコマース
・動画コマース
・無料ビデオプレビュー
・無料のスポーツ試合チケット
・LIVEイベント
・チャレンジ企画
最近よくあるのは3日間チャレンジプログラムとかのチャレンジ企画ですね。これは3日間で、何かを達成することにチャレンジしましょうというもので、これまでのオンラインプログラムは、動画を渡してワークを行ってもらおうとしても、大体がワークをやらないので、変化を与えにくいというものがありました。
そこでチャレンジ企画として、ワークに取り組むのが当たり前というフレーミングを行ったフロントエンド商品となります。
4)コンサルティングや診断系
次にコンサルティングや診断系ですね。これはコンサルタントや、ホームページの作成業者さんだったり、何かシステムなどを販売している会社によくあるフロントエンド商品です。
そして、BtoBなどの会社にとっても有効なフロントエンド商品であり、特徴としては対面で行うものが多いので、信頼関係を築きやすく、失注や離脱することが少ないフロントエンド商品でもあります。
では具体的にどのようなものがあるかというと、、
・無料見積もり
・無料個別プランニング
・無料コンサルティング
・無料セッション
・無料コーチング
・無料相談
・無料診断(Webサイト診断・LP診断など)
・無料分析(広告パフォーマンス分析など)
無料見積もりなんかも、一昔前はお金がかかっていましたが、今や見積もりだけでお金を取るなんてとんでもない会社だ!となりました。
そして無料コンサルティングや無料セッションなんかの場合は、何かしらのトレーニングプログラムや、ジムなどでは当てはまるかなと思います。
他にも診断や分析は、医者と患者の関係を見込み客と築きやすいので、その後のバックエンド商品が売りやすいという特徴があります。
他のフロントエンド商品に比べて、バックエンド商品への商談に繋がりやすく、最初から関係を築きやすいので、積極的に持っておきたいフロントエンド商品の1つですね。
5)コミュニティ・イベント系
そして次にコミュニティ・イベント系です。これは、コミュニティを運営している人やオンラインサロンなんかを運営している人にとっては、必ず検討しておきたいフロントエンド商品の1つです。
あとは、フォーラムや研究会を行っているコミュニティも、以下のフロントエンド商品を持っているといいかもしれません。コミュニティ運営の鍵は、内輪感を少し出しつつも、最初の人を歓迎するかが重要です。
・コミュニティサイト
・オープンディスカッションフォーラム
・無料のコミュニティイベント
・交流会やネットワーキングイベント
・無料Facebook Liveイベント
・無料Meetupイベント
・無料オンラインチャットサポート
・無料のマスターマインドグループ
・Facebookグループ
・LINEグループ
・Q&Aセッション
・チャットボット
・ライブチャット
上記のようなもの、少しイメージがつきにくいかもしれませんが、昔一度チャットワークを使った無料相談グループを作ったことがあります。
そこでは、即時返信ではないけれど、マーケティングやセールスライティングに関する質問・疑問を投げ込んでもらって、僕が回答する。回答した内容はずっと溜まっていくので、そこに入った人からすると、たくさんの質問と回答が見れるという場所です。
溜まった質問は後でQA形式のレポートなんかにも活用できることもあり、今後もまたやってもいいかななんて思ってますが、少し労力はかかるので、労力がかかっても大丈夫という方にはオススメできます。
6)物理的な商品・サービス系
さて、ここからは少し毛色が違って、物理的な商品・サービス系を扱っている企業や事業者向けのフロントエンド商品の解説です。
そしてもしあなたが、物理的な商品・サービス系に対して少しでもコストを払ってもいいと思えるなら、必ず取り組んでみて欲しいフロントエンド商品になります。なぜなら、物理的な商品・サービスがあると、長期的なリピート率が高まるからです。
実際、あるサブスクリプション(継続商品)で、物理的な紙媒体を無くしたことがあります。すると、継続率は30%近く落ちました。30%ってかなりの数字なので、すぐに戻しましたが、少しでもコストをかけてもリピート率をあげたいという事なら、物理的な商品・サービス系は検討してみるのがオススメです。
・イベントチケット
・書籍の配送
・無料延長保証
・自社ブランド品
・無料のトレーニング器具
・無料のVR体験
・無料ワークショップ
・無料の施設見学
・無料のスポーツ試合チケット
・小冊子
・パンフレット
・カタログ
・絵葉書
・施設の無料ツアー
・プレゼント(スタバの豆とか)
これらの物理的なフロントエンド商品は、販売した後の長期的な関係性が構築でき、リピート率が高い(LTVが高い)傾向にあります。
ただ、物理的なフロントエンド商品はコストがどうしてもかかりやすいので、最初は出来るだけコストを抑えたもので実施するのをお勧めします。
最もオススメするやり方は、オンラインのPDFレポートなどと、物理的なものを組み合わせる方法です。
過去行った方法だと、インターネット上でPDFレポートの前半部分を請求してもらい、その後、後半部分がさらに読みたければ、住所入力をしてもらい、物理的なレポートを郵送するという方法を行っていました。
この方法のメリットとしては、メールアドレスと住所の2つのリストが手に入るので、その後のダイレクトメールなどに繋げやすい。そして物理的なものを送ることで、ちゃんとした会社なのだと認識してもらいやすく、その後のリピートにも繋がりやすいというメリットがあります。
広告の場合、物理的なものを最初に購入してもらうのは、広告コストが上がりやすいですが、この方法だと、広告コストは抑えつつも、その後のリピートに繋げやすいので、塾やスクールなどから、弁護士事務所、インフォ系のビジネスなど、ほぼあらゆる業種にオススメの方法となります。
ただ、デメリットとしては、郵送が面倒なのと、どうしてもコストがかさんでしまうので、ある程度キャッシュがあるか、少人数でも確実な見込み客を獲得したい場合に限った方が良い時もあります。
7)特典・割引・トライアル系
次に紹介するのは、特典・割引・トライアル系のフロントエンド商品についてです。
ただ基本的に、大体のフロントエンド商品と組み合わせて使ったほうが最も効果的なので、これまでに紹介したものにプラスαできないか?という視点で見てもらうのが良いでしょう。
・新規顧客限定の割引
・クーポン
・友達紹介キャンペーン
・早期注文割引
・送料無料
・次回購入割引券
・有料トライアル
・ロイヤルティプログラムの無料スタート
・リピート顧客向け特典
・カスタムメイド製品の無料提供
・無料アップグレードオプション
・ポイントシステム
・特別プランやパック
そして見てもらったら分かるかもですが、ロイヤル顧客にするためのものや、リピートを促すためのものも入っています。フロントエンド商品といえば、『新規の見込み客を獲得するためのもの』と捉えがちですが、『見込み客を顧客に転換するもの』としても使えます。
ただ、この特典系を考える際に、必ず景品表示法について調べてから行ってください。よくプレゼント〇〇円分!との記載があるLPがありますが、あれはほぼ99%違法です。そして、そのような提案をしてくるセールスライターやマーケターがいたら、その人と一緒に仕事をするのは考え直した方が良いかもしれません。
8)パーソナル・カスタマイズ系
次に紹介するのは、パーソナル・カスタマイズ系です。これはあなた専用のメニューですよということで、自分に最適なものなんだと認識してもらいやすく、フロントエンド商品の成約率を高めることができるという効果があります。
・カスタマイズ無料商品
・カスタムメニュー作成
・無料個別フィードバック
・カスタマイズされた無料提案
・パーソナライズされたロードマップ
・個別目標設定セッション
・パーソナライズされたトレーニングプログラム
・パーソナライズされたフィットネスプラン
・パーソナライズされたキャリアアドバイス
・カスタマイズされた商品オファー
例えばジムなんかだと、最初に個別の筋トレメニュープログラムを作ってあげるとかすると、自分のためのプログラムなんだということで、その後の入会率が高まります。
実際にあったのが、還付金請求や、鬱病に特化した障害年金の企業では、最初に情報を入力してもらい、いくら返ってくるのか。もしくは概算でいくらの金額が手に入るのか?という診断書のようなものを後日郵送してくれるという方法で、インターネット上で効率よくリストを獲得しています。
9)楽しみやエンタメ系
これは楽しみやエンタメ系と書いてますが、ショッピングモールなんかだとよく見るものです。
例えば携帯電話の販売やネット回線、ウォーターサーバーの契約なんかだと、まず抽選などをしてもらって、その後に販売関連の話をしたりとかしますよね。
それ以外にも、コミュニティ系でもまず無料のピザパーティーなどに来てもらって、その後にコミュニティのセールスが始まったり、倫理法人会なんかは、無料の交流会に来てもらって、そこで倫理法人会の説明をしたりという地域もあります。
・抽選
・景品
・無料の宝探しイベント
・無料のライブミュージック
・無料の映画試写会
・無料アートクラス
・クラフトナイト
・無料カクテルパーティー
・ゲームナイト
・無料のスタンドアップコメディショー
・無料カクテルパーティー
・ライブイベント
・料理教室
・無料映画試写会
これらは、楽しんでもらい、コミュニティ感を感じてもらうことができるので、あまり強引なセールスをするとかなりの反感を受けますが、そうではなく、コミュニティに所属してもらうことが楽しいとなるまで待つのがベストです。
フロントエンドの価格はいくらが適切なのか?
では、フロントエンドを考える際の価格はいくらが適切なのか。先に結論をお伝えすると、残念ながらテストをするしかありません。ですがその時、最も安い金額からテストを行うのがベストです。
まず、なぜテストをするしかないかというと、
・いくらくらいまでの赤字なら会社のキャッシュフローが回るか。
・広告費にいくらつぎ込み、どのような広告を出すか。
・広告での獲得コストが何ヶ月目に回収できるのか。
などの変数が多いためです。
実際にあった例でお伝えすると、
あるオンラインコンテンツを販売するために、フロントエンドのレポートを作成したことがあります。その際、フロントエンドの価格は無料でした。無料のフロントエンドかつ、知名度もある講師の名前で販売していたため広告もヒット。月に数百名の新規顧客が獲得でき、新規獲得はとても順調でした。
ですが、広告費などの獲得コストをどれくらいで回収できるのかを計算してみると、36ヶ月かかることが分かりました。
幸いこの会社には、それだけの回収を待てるキャッシュがあったため、36ヶ月かけて黒字に転換することができましたが、ほとんどの企業では回収が成り立たない可能性が高いのではないでしょうか。
また、あるフロントエンドの書籍を出した企業は、Google広告とMeta広告の2つを運用していました。ですが同じフロントエンド、同じ価格にもかかわらず、Google広告とMeta広告での回収見込みが全く違ったのです。
Google広告の場合は、広告での獲得コストを3ヶ月で回収できましたが、Meta広告の場合は回収に1年程度かかっていました。
Google広告の場合は検索連動型の広告だったため、顧客の商品やサービスへの購入意欲が高いのですが、Meta広告の場合は購入意欲が低いため、このように同じフロントエンド、同じ価格でも、回収見込みが大きくずれることもあります。
そのため、フロントエンドをいくらで出すかは、結局はテストをしてどれくらいで回収できるかを計算しないといけないため、フロントエンドの価格をいくらに設定するかは、テストしてみないと分からないということです。
ただ、気をつけてほしいのは、テストする時の金額は、最も安い価格でテストをすることが重要です。
なぜなら、フロントエンドを作ったとしても、購入してくれる顧客が0だと、何のテストにもならないからです。そのため、
1、フロントエンドを作る。
2、最も安い価格設定を行う。
3、回収見込みを計算して、金額を少しずつ上げる。
4、獲得コストの回収見込みと、新規の数を計算して、ベストの価格を決める。
という流れでフロントエンドの価格テストを行うのが最も最適です。
見込み客が集まるフロントエンド商品4つのポイント
まず、フロントエンド(集客)商品を作る際のポイントですが、次の3つです。
ポイント1:顧客が欲しいものを渡せ。
ポイント2:いますぐ解決するものを渡せ。
ポイント3:パッと見で分かるものを渡せ。
ポイント4:最後につながるものを渡せ。
ポイント1:顧客が欲しいものを渡せ。
とは、最終的にあなたが販売したい商品の1ポイントなどではなく、顧客が今すぐ欲しいものを渡さないといけないということです。
例えば僕の場合、長期的にはメールマガジンを発行するということが売上を上げるために必要な要素と考えていますが、見込み客が今すぐ欲しいものは、「今すぐ売上を上げる方法」です。
ここで僕が、メールマガジンの発行の仕方というフロントエンド商品を作ったとしても、見込み客からしたら、
「そんなんいいから、今すぐ売上あげたいんだけど!?」
と言われるのがオチ。なのでここで渡さないといけないのは、顧客が”今抱えている悩みを解決する”フロントエンド商品ということです。
ポイント2:いますぐ解決するものを渡せ。
これは先ほどのものと少し似ていますが、顧客の悩みを長期的に解決してくれるものか、短期的に解決してくれるものなら、短期的に今すぐ解決してくれるフロントエンド商品を渡せということです。
例えば先ほどの例だと、
1年後に現金100万円になる方法
よりも、
明日すぐに現金10万円が手に入る方法
を、フロントエンド商品として渡さないといけないということ。見込み客・顧客は、”今”困っています。なので、今すぐに解決できる方法を探して、インターネット上を彷徨っていることが多い。
なので、今すぐ解決できるものを用意する必要があります。
ポイント3:パッと見で分かるものを渡せ。
これには2種類の意味があります。
まず一つ目が、「パッとみて分かりやすいタイトルにするべき」とは、タイトルのことでうす。例えば僕が、
「今後10年以上大切になりつつも、今も大切な、税務署にも確認した明日現金10万円がもらえる方法」
という長ったらしい、よく意味が分からない商品を置くよりも、
「明日現金10万円手にはいるファーストキャッシュ戦略」
という名前の方が、まだパッとみて意味が分かりますよね。長ったらしいタイトルや、パッとみてよく分からないタイトルをつけるのではなく、パッと1秒みて、「あっ、良さそう!」と思えるようなタイトルがついたフロントエンド商品を作る必要があるということです。
そしてもう一つが、「パッとみて、良さそうと思えるパッケージかどうか」です。
人は見た目で判断するとはよく言いますが、例えばもしあなたが、PDFレポートのフロントエンド商品を作るとします。その時、最も力をかけないといけないのは、タイトル。そして次に、表紙などのデザインです。表紙などのデザインは、デザイナーさんに依頼してもいいレベルで力をかけるべき。
それくらい見た目は大切ですし、見た目でフロントエンド集客のセールスレターの成約率が10%変わることもあります。それくらい人は見た目が重要ということですね。なので、必ずタイトルと、見た目に力を入れること。
ポイント4:最後につながるものを渡せ。
そしてポイント4つ目、最後に繋がるものを渡せ。とは、最終的にあなたが販売したい商品に繋がるフロントエンド商品を作らないといけないということ。
これは実際にあった話なのですが、ある住宅販売展示場に行くと、メロンがもらえたそうです。なんでメロン?と思いますが、なんでも担当者が好きだからだそうで…。ただ、たくさんの人が来場したそうなんです。みんなメロン大好きなんですね。とはいえ、結果としては全く成約に繋がりませんでした。
ではいったいなぜか。おそらく、住宅展示場に来られる方は、メロンが欲しい人であり、住宅を新しく建てたい人ではなかった。というのが答えではないかと。
なので住宅を販売したいのであれば、住宅を建てるときに気をつけるべき5つのポイントというセミナーを実施したり、住宅を最終的に欲しい人が、今すぐ解決したいことを解決するためのフロントエンド商品を作る必要があるということなんです。
メロンは流石に笑い話ですが、実際こういう事例はたくさんあります。かならず今日あげた4つのポイントを確認して、フロントエンド商品を作ってみてください。